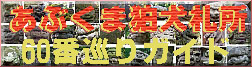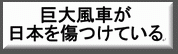2012/10/07
鹿沼ぶっつけ秋祭り2012(2)

さて、助手さんはドアップの写真ばかり撮り続けていた。こうなると、この彫刻はどの屋台? と、後から検証しなくてはいけない。しかし、これまたクイズみたいでとても面白いではないか。
例えば上の写真。彩色が施されている屋台は、石橋町、下材木町、下横町、御成橋町、戸張町、久保町、上材木町だ。
さて、この7つのうちのどれでしょう。

クジャクもいますね

ん? 「を」の町印がある。これで「御成町町」と確定

大正6(1917)年制作 彫刻師:石塚広次(大正10年頃に後付け) 戦後に屋台を黒漆塗りに、彫刻に彩色を施し、白木屋台から彩色屋台に生まれ変わった

これはどこの? 彩色屋台だが、御成町の屋台には栗鼠はいなかったはず……

どうも2台並んでいたようだ。左のが御成町の屋台。手前にあるのは金獅子が見えているので上材木町の屋台だ

この丸彫り(まるまる独立した立体彫刻)の大きな獅子像が目印。前後の鬼板位置にある。文政11年制作

ではこれは? 下という字が見えているので分かる。半纏にもちゃんと町名が入っている。下田町の屋台。文久2(1862)年制作。彫刻師は石塚吉明。箱棟の高さがいちばん高い屋台だそうだ。
天神町の屋台(江戸時代だが詳細な年代不明)に非常に似ているので、パッと見ただけではなかなか区別がつかない。
以下、秋祭り公式ガイドブックの解説をまとめてみた。
■下組 7町
石橋町 文化9(1812)年制作 彫刻師:神山政五郎「菊政」 色街なので菊の花や鳥の極彩色彫刻が中心
下材木町 天保3(1832)年制作 彫刻師:磯辺儀左衛門信秀(通称「凡竜斎」) 全面、龍で統一。屋根は布張り。屋根裏は朱塗り
寺町 昭和3(1928)年制作 彫刻師:山口忠志 前面鬼板に大きな竜虎像
蓬莱町 昭和30(1955)年制作 彫刻師:笹川無門(富山県出身) 脇障子に鷹。欄間に十二支
鳥居跡町 昭和30(1955)年制作 彫刻:富山懸井波彫刻協同組合 花鳥図の豪華絢爛な構図
仲町 天保7(1836)年制作 彫刻師:後藤周二正秀、磯辺儀兵衛ら磯辺一族 白木彫刻に部分彩色。鬼板は飛龍。懸魚は玉取の龍。
麻芋町 安政3(1856)年制作 彫刻師:後藤音次郎 鬼板と毛魚を唐獅子牡丹の構図で構成。箱棟に丸彫りの子獅子3頭。高覧に磯辺杢斎彫刻の金龍
■田町下組 6町
中田町 天保年間制作 鬼板に3頭の龍、懸魚にも龍。車隠しは唐獅子牡丹。籠彫りの珠つき。
下田町 文久2(1862)年制作 彫刻師:石塚吉明 箱棟の高さが最も高い。鬼板は龍。
下横町 文化年間制作 小型だが、まだ幕府が華美禁止令を出す前の作なので彩色を施している。鬼板と懸魚に芙蓉。脇障子は額付きの明かり障子。
銀座一丁目 文化11(1814)年制作 彫刻師:磯辺凡龍斎 黒漆の上に白木彫刻。彩色が禁止された直後の様式を伝える珍しい作。脇障子の滝の上下に鷲と猿の構図が特徴的
末広町 明治15(1882)年制作 鬼板・懸魚に唐獅子牡丹。柱飾りがあり、葡萄と栗鼠の彫刻が楽しい
東末広町 昭和57(1982)年制作 彫刻:辻幹雄ら多数。鬼板・懸魚は荒波からの昇り龍
■田町上組 7町
上田町 文政5(1822)年制作の屋台が焼失し、昭和28年に復刻。元の屋台からは黒漆の脇障子(石塚知興・彫刻)を引き継ぎ、他の彫刻は現代の名工・黒崎嘉門が担当。もしかすると元の屋台より豪華なものになっているかもしれない
文化橋町 昭和33(1958)年制作 彫刻師:辻幹雄ら 町内に住む彫刻科たちによって現在も彫刻が追加されている
朝日町 昭和29(1954)年制作 彫刻師:阿久津若陽、雲蝶ら 鬼板に鳳凰。懸魚に菊水(若陽・作)。欄間の花鳥図は雲蝶の作。
府中町 平成2(1990)年制作 彫刻師:黒崎嘉門 鬼板の大獅子が特徴
府所町 昭和63(1988)年制作 鬼板と懸魚が富山県の彫刻師、脇障子・外欄間・車隠・水引が台湾の彫刻師による「日台合作」の屋台。屋根には水晶玉を抱く龍
府所本町 平成5(1993)年制作 彫刻は台湾の彫刻師によるもの。二匹の龍が珠を奪い合う構図。高覧下には鯉の滝登りも
上野町 昭和58(1983)年制作 彫刻師:黒崎嘉門 大工は鹿沼の元野兄弟。すべて「現役の鹿沼職人」の手で作られた屋台
■上組 7町
久保町 文化10(1813)年制作 屋台のまち中央公園の展示場に常設展示されている1台。時代が最も古く、幕府の華美禁止令が出る前の黒漆塗り彩色様式。屋台内部までが漆塗りで、金泥や金物もふんだんに使った豪華絢爛な作り。鬼板と破風が一体化して二匹の龍が絡み合っている
天神町 江戸時代制作 彫刻師:磯辺儀兵衛敬信。鬼板と懸魚に二匹の龍。琵琶板と外欄間に尾長鶏と梅。脇障子は竜虎。障子周りに龍。高覧下と車隠しに唐獅子牡丹。これでもかというくらいのボリュームで彫刻を施している
上材木町 文政11(1828)年制作 彫刻師:石塚知興 鬼板に丸彫りの金獅子。絢爛な螺鈿細工も施されている豪華な作り
戸張町 文政11(1828)年制作 彫刻師:石塚知興・吉明父子 文政12年に白木彫刻屋台として完成した後、弘化3(1846)年に漆塗り彩色が施された。鬼板には獲物を狙う大鷲。懸魚に藤に身を隠す3匹の猿という構図。
泉町 平成8(1996)年制作 彫刻師:黒崎嘉門 鬼板と懸魚は玄武。欄間、水引には花鳥。高覧はアーチ型
御成橋町 大正6(1917)年制作 彫刻師:石塚広次(大正10年頃に後付け) 戦後に屋台を黒漆塗りに、彫刻に彩色を施し、白木屋台から彩色屋台に生まれ変わった
WEB用に加工した写真だけでも1000枚くらいあるので、次のページからは、ほんのダイジェスト版を掲載する。
詳細版は別の場所に後日、町別に整理して載せていこうかと思っている。
「ガバサク流」が推すデジカメ パナソニックLX7、LX5、ソニー RX100、フジ X-S1
詳しくは⇒こちら
たくき よしみつ 新譜・新刊情報
音楽アルバム『ABUKUMA』
『3.11後を生きるきみたちへ ~福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書)
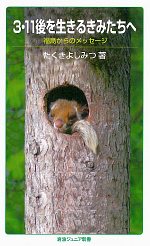

|
『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ)
『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言
第1章 あの日何が起きたのか
第2章 日本は放射能汚染国家になった
第3章 壊されたコミュニティ
第4章 原子力の正体
第5章 放射能より怖いもの
第6章 エネルギー問題の嘘と真実
第7章 3・11後の日本を生きる
■今すぐご注文できます
 で買う で買う

⇒立ち読み版はこちら
|
|---|
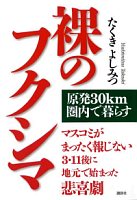
|
『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ)
ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。
第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか?
第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実
第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった
第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様
第5章 裸のフクシマ
かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛
■今すぐご注文できます
 で買う で買う
⇒立ち読み版はこちら
|
|---|
 一つ前へ abukuma.us HOME takuki.com HOME
一つ前へ abukuma.us HOME takuki.com HOME
 次の日記へ
次の日記へ
↑タヌパックの音楽CDはこの場で無料試聴できます
Flash未対応ブラウザで、↑ここが見えていない場合は
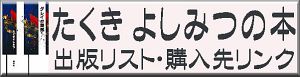


 |
(バナナブックス、1700円税込)…… オールカラー、日英両国語対応、画像収録400点以上という狛犬本の決定版。25年以上かけて撮影した狛犬たちを眺めるだけでも文句なく面白い。学術的にも、狛犬芸術を初めて体系的に解説した貴重な書。
 で注文 で注文
|
 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ


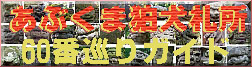
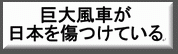









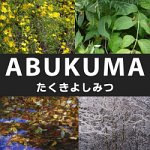
 『ABUKUMA』(全11曲)
『ABUKUMA』(全11曲)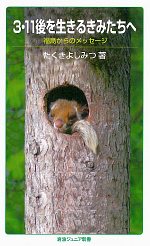
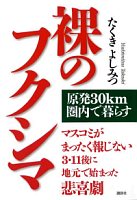

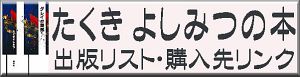


 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ