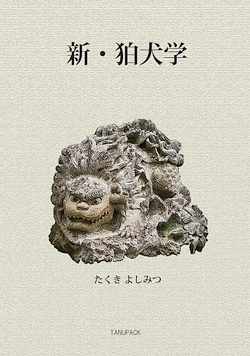次は佐野市高山町というところにある熊野神社。
ここはかなり分かりづらい場所だった。進入路が細くて、どこまで車で入れるのか分からない不安さを抱えながら到着。時刻は12時半。

本来、こういう神社なのだが、正面は車が入れず、沢が流れていて田圃が迫る地形。裏手から入る形になったため……

いきなりお尻からコンニチハ、になってしまった。

ここも阿吽が逆位置に置かれている。

吽像は角あり。


阿像は宝珠。さっきの浅田神社と同じパターンだが、こちらはすっくと蹲踞していて、石を縦に使っているので洗練された感じを受ける。。

吽像の顔。


阿像の顔。




口の中もかなりていねいに彫り込まれている。

阿像の尾。スパッと切れているが、元々なのか?

阿像の尾はスッと伸びているのだが……。

お約束の脚。

台座の泥をある程度取ってみたが、年号は見あたらなかった。茂呂 黒田……地名かな。

そばの手水鉢には天明7(1787)年の年号がある。さっきの浅田神社の狛犬が寛政7(1795)年だから、この狛犬もほぼ同じ時期ではなかろうか。
……と書いて、一旦WEBにUPしたところで階下に降りて行ったら、どういう偶然か、ちょうど佐野市郷土博物館の山口館長から「史談」会報37号というのが届いていて、そこに掲載された氏の「江戸時代に奉納された佐野の狛犬」という記事の中でこの狛犬の奉納年が安永3(1774)年であると書かれていた。
台座に「安永三甲午九月吉日」と刻まれているそうだ。天明7(1787)年よりさらに古いわけで、すごい。
社殿もいい!

目立たない山の中の神社なのだが、社殿もよくみると味わい深い。屋根の大棟に青海波の装飾。

鬼瓦もカッコいい。




内陣上の屋根。

社殿の木彫。


社殿の木彫は鹿沼や宇都宮の彫刻屋台や天棚と同系統(磯辺系)の彫師によるものだろうか。なかなかのもの。
こんな場所に……と言っては失礼だが、すごいものが揃っていてビックリだ。
さて、次にリストアップしたのは西丘神社だが、ここからの直線距離はさほどないのだが、渡良瀬川を挟んでいるので、ものすごく迂回しないといけない。
ひたすら走る。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ