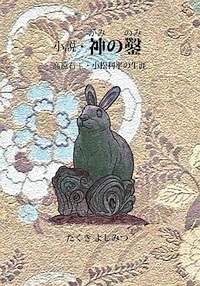阿像。コブコブマッチョな身体と彫りの深い?顔の取り合わせが不思議な感じ。


吽像。


辛うじて寛政10(1798)年の銘が読み取れるが、もうすぐ完全に消えてしまいそうだ。

入り口のケヤキの巨木のそばにいて、最初に出迎えてくれる。

阿像の顔。口の開き方が控えめというか、石工さんの美学のようなものを感じる。



吽像の顔。閉じた口元もシワシワしている。

鬣もていねいに刻んでいる。1700年代の狛犬としてはかなり高度な技術を見せている。

尾もこの通り、手抜きなし。

背中はつるんとしているのが面白い。また、阿吽で尾のデザインを完全に変えている。

鬣は優美に、身体はマッチョにコブコブもいっぱいつけて……。


足元担当の助手さんは、爪先に刻まれた毛のうねりも見逃さない。

よく考えると、かなり個性的な狛犬なのだが、全体にまとまりがあるため、強烈な印象を残すタイプではない。じっくり見ていくと、石工さん独自のこだわりや美意識が読み取れて面白い。
さっき見てきた大前神社の天保の狛犬などより古いのに、技術的にははるかに上で、これも江戸石工なのか、それとも地元の名石工なのか……。
さて、次も変わり種なので、ページを分けて紹介しよう。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ