 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ
のぼみ~日記 2020

体全体が黄色っぽく、前翅の前縁が茶褐色のカゲロウ。尾は3本ある。……なるほど。
平地・低山地の河川周辺で見られ、灯火にもよく飛来する。
幼虫は、ゆるやかな流れの、川底の石の下にひそんでいる。
(昆虫エクスプローラ)
幼虫は成熟すると、水面または水辺で羽化して亜成虫となり、さらにもう1回脱皮して成虫となる。亜成虫という形質は、ほかの昆虫類にはみられず、カゲロウ目に固有のもので、成虫とよく似た形態をもつが、性的には未熟で、飛ぶ力も弱い。また、成虫よりもやや大きく、灰色がかっており、肢や尾は太くて短く、はねは不透明である。
(略)幼虫期間は平均1年、長いもので3年を経過するが、亜成虫の時期はおよそ1日ぐらいのもので、成虫も1日程度、短い種で4~5時間しか生存できない。このように成虫期間の短いことから、はかないもののたとえに用いられ、分類階級の目の名称もギリシア語のephmeros(わずか1日の命の意)に由来する。また、カゲロウの名は、成虫になってから飛び交うさまを陽炎(かげろう)になぞらえたもので、英語のmayflyは5~6月に羽化するものが多いところから出た。
(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説より)




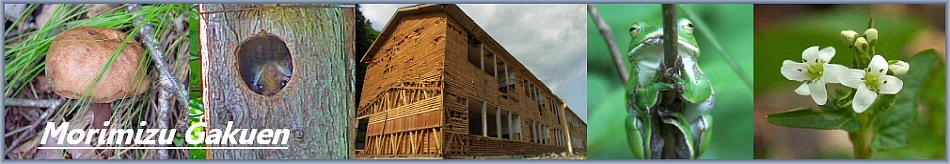



|
|
|---|