ご近所の石仏シリーズで、年号が読み取れるもので最古なのはこの祠の中の三体あるうちの横の一体(如意輪観音像?)に刻まれた「享保十六(1731年)年辛亥。奉納六十六部供養尊像 十月十九日」。
で、改めてこの祠全体をよく見ると、真ん中の大きな像、今までは深く考えずに地蔵菩薩だと思い込んでいたのだが(赤いエプロンや帽子のせいか)、よく見ると脚を組んだ半跏趺坐像。
興福寺には国宝の地蔵菩薩半跏趺坐像というものがあるし、
「地蔵菩薩半跏座像」で画像検索してもいっぱい出てくるので、このスタイルはあるのだが、普通、石の地蔵のイメージはスッと立っている姿なのだよね。改めて思い浮かべると、このあたりではこのタイプ(座像)の地蔵菩薩像がかなりある。
地蔵菩薩が脇侍を従えるというのはあまり聞いたことがないから(如来ではなく菩薩だし……)、左右の像は別々にあったものをここに集めてきたのだろう。
で、地蔵菩薩の蓮華座に、猫のような彫り物があるのがとても興味深い。

ネコに見えるけれど、違うのかなあ……


台座がものすごく高い(本体地蔵像と同じくらいある)のも興味深い。これは「願主○○敬白」と読める。

左隅にある罵倒観音像(文字だけのタイプ)は明治になってから。やはり、別々のものをここに集めたのだろう。

そのまま、さらに先の墓地へ。月が出ているねえ。

この小さな半跏思惟像が気になっていたのだが、年号は読み取れそうもない

2019/02/18

今日もライチェルと石仏の確認。桜の木の下の地蔵菩薩は、背中側に文字が刻まれているのだが、読めないなあ。「明」と「講中」はなんとか読める。明治かな?

今日は県道を横切って、さらに離れた墓地へ。墓地は新しく直されているが、片隅には古い墓が残っている。

新しい大理石の台石の上に置かれた地蔵菩薩像。左手に如意宝珠、右手に錫杖を持っている。

台座に何か刻まれていたかもしれないが、新しくなってしまっているので分からない。本体には文字は刻まれていないようだ。明治期くらいだろうか。

その墓地のそばにある庚申塔。昭和55(1980)年に、まだこの土地で庚申講が存在していたという、むしろその新しさに驚く。御猪口が供えられているので、今も講は残っているのかもしれない。岩崎(地名)の2軒が続けている講なのだろうか。

 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ



















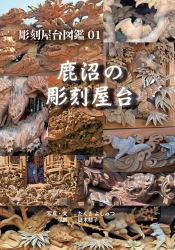
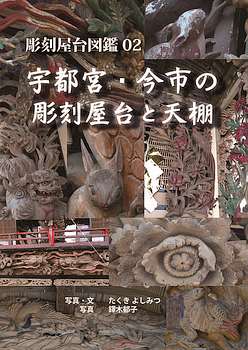
 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ