2社目は少し南下して岩崎町(いわざきちょう)の八幡神社。ここには3対並んでいた。いちばん手前のが江戸時代だと思うが、残念ながら年号は見あたらず。これは今まで見てきたはじめタイプの中でも、飛び抜けてうまい。これを見られただけでも雨の中出てきた甲斐があった。

ようやく見えてきた

こんな配置で3対が石段上に並んでいる


なんといってもこれ! 江戸時代だろうが、とてもよくできている


吽像のほう。破損や摩耗もほとんどなく、大変素晴らしい状態

隣のチビが「兄貴~」って呼びかけているように見える


阿像の尾↑ 吽像の尾↓ 微妙に変化させている


どちらにも頭には小さな穴の跡があり、何かがのっていたのか、それともただ削れたのか? 蝋燭立てにした跡か?


阿像の前脚。走り毛が下向きになっているが、ただのデザインだという認識だったのか? 前脚の後ろ側に縁取り的に刻みを入れている↓ところも、石工さんのセンスのよさがうかがえる


そして、この垂れ耳!

鼻や口の縁取りもていねいで、いい仕事してますねえ。吽像はあご髭が歯と一体化?していて、なんだか変だけど

阿像のくちびるなども、曲線の描き方がとてもアートしていて、感心してしまう

腹の下も見てみたが、銘はなかった。いつ頃の作品なのだろう
 一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ
一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ























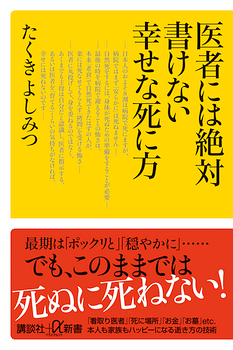
 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ