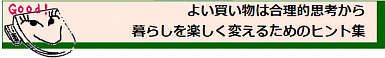写真集『鹿沼の彫刻屋台』が一段落したので、また「死に方」の本の執筆に戻っている。
死ぬなら家で死にたい。病院では死にたくない……と思っている人が多いのに、実際には病院で死ぬ人が8割。
昔は逆で、自宅で死ぬ人が8割だった。
国は病院で死ぬ人の数をなるべく減らしたい。なぜなら
病院死は「コストがかかる」からだ。
昨夜書いた部分を少し抜き出してみる。本にしたいと思って書いている原稿は「ですます体」で書いているが、端折って「である体」に直した。
●「90日ルール」を知った上で病院とつき合う
入院が必要な患者であっても、同じ病院には3か月以上はいさせてもらえない、という「90日ルール」については、今では多くの人が知っている。
表向きは「退院して自宅療養や自宅介護できる人まで入院させていると、緊急を要する患者の受け入れができなくなる」というような説明がされているが、実際には「90日以上入院させていると病院がつぶれる」からだ。
まず、病院の一般病棟には「看護ランク」が決められていて、そのランクによって「平均在院日数」が定められている。
患者対看護職員の数が7対1の病棟だと平均在院日数は19日以内、10対1の病棟では21日以内、13対1だと24日以内、15対1だと60日以内……というように。
つまり、
患者1人あたりの看護職員数が多い「手厚く面倒を見てくれる」病棟ほどいられる日数は短い。
入院患者を受け入れると、病院は投薬や検査などの治療にかかる料金の他に「入院基本料」というものを請求できる。
7対1病棟の場合、入院基本料は1591点(1万5910円)/日で、入院14日目まではこれに450点(4500円)加算されて2万410円。同様に15~30日目までは1920円加算されて1万7830円、31~89日目までは加算ゼロで1万5910円となる。
だから、病院としては14日以内で退院させられる人は退院させて、新たな患者を受け入れたほうがいい。
で、これが90日を超えると、医療業界では通称「まるめ」といわれる「包括支払制度」にされてしまい、点滴をしようが投薬しようが全部ひとまとめでいくら、という計算になる。その一定額というのは病気の内容などによるが7500円からで、高度な治療を必要とする特殊な場合でも上限は1万8100円。それ以上はどれだけかかっても請求できなくなる。
この「まるめ」には、検査、投薬、注射、病理診断、エックス線診断(単純撮影)、創傷処置・酸素吸入・留置カテーテル・鼻腔栄養……等々が含まれるので、
病院としては入院90日を超える患者には治療をすればするほど赤字を抱え込むことになり、死活問題なのだ。
で、これは逆に見れば、
「入院初期では、高額な医療行為をすればするほど診療点数が稼げる」ということになる。
例えば、自宅で療養していた人の容態が悪くなり、病院に運ばれた場合、受け入れた病院では入院ゼロ日からの計算だから、いくら本人が楽に死にたいと望んでも、運び込まれるなり、レントゲン、血液検査、酸素マスク、ステロイドやら抗生剤やら強心剤やらの点滴……と、ありとあらゆる高額医療行為を施されてしまう。病院としては「やれることは全部やりたい」。入院直後はそのほうが儲かるからだ。
家族も「どうか一分でも命を長らえさせてください」などと無責任なことを言って、これから死のうとしている人を無用に苦しめる。
これから死ぬ人にとっては、これがいちばん恐ろしい。
「看取り」を巡る医療機関と国の攻防
国が「90日ルール」を強行する理由は、金がかかる病院死を減らしていきたいからだ。
死亡前1年間にかかる1人あたりの医療費はどんどん膨れあがっており、中には3日で500万円、1週間で1000万円の医療請求などもある。
平均でもざっと300万円弱はかかっている(厚労省、後期高齢者医療制度担当者の問題記述、「終末期医療の動向」日本医師会雑誌掲載、東京都老人医療センターにおける終末医療費の解析など、複数のデータから概算)。
これから大量死時代を迎えるというのに、これでは医療保険制度が維持できなくなる。国が国民に「病院ではなく、自宅で死んでください」とお願いしたくなるのは当然だろう。
90日ルールもあって、病院で死ぬ人の割合は2005年のピーク時82.4%に対して2012年では78.6%と、わずかだが下がっている。
しかしこれは、2000年に登場した介護保険制度によって、特別養護老人ホーム(特養)、グループホーム、有料老人ホームなどが増えてきたことも大きな要因で、これらの施設での死亡率は3.5%上昇している。つまり、
病院で死ぬ割合がわずかに減った分は自宅死に移行したのではなく、介護施設に移されたといえる。
その特養などの介護施設も、入所者が施設内で死ぬのは望まない。死にそうになると、「ここでは医療行為ができないので」と、病院に送り込む。
病院は病院で、治療をしても回復が望めない患者を受け入れ、死ぬまで入院させておくのは嫌がる。長引けば「90日ルール」によって経営が脅かされるからだ。
そこで厚労省は、特養やグループホームなどの居住型介護施設で入居者が亡くなった場合、介護報酬に「看取りポイント」ともいえる加算点をつけられるようにもし、2012年にはこれを有料老人ホームにも広げた。「施設内で死にそうになった老人を病院に連れ込まないでくれ。なんとかそこで看取ってくれ」というわけだ。
介護施設で、過剰な医療処置を受けずに自然死に近い状態で看取ってもらえるなら、それもひとつの理想的な死に方だろうが、現状ではまだまだそこまで「看取り」に対して積極的に向き合っている介護施設は少ない。
なにより、よい施設に入ることは簡単ではないし、金もかかる。
●「家で死にたい」親と「家で死なせたくない」家族
日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団別の調査では、「余命が限られた場合、自宅で過ごしたい」と答えた人は約80%だそうだ。
しかし、内閣府が発表している「高齢社会白書」(平成27年度版)によれば、約55%の人は「自宅で死にたい」と答えたが、病院などの医療施設で死にたいと答えた人も約28%、老人向けサービス付きの住宅や特養などの介護施設で死にたいという人と合わせると約35%にのぼる。
おそらくこれは、本音では家で死にたいけれど、家族に迷惑をかけるのは嫌だから、病院や介護施設で死ぬのは仕方がない、という気持ちからだろう。その証拠に、同じ調査で「子供の家で死にたい」と答えた人は1%もいない。
看取る側の家族にしても、最後の処置は素人にはできない、病院に任せるしかないという考えが強い。
しかし、一旦病院に運び込まれたら最後、拷問に等しい無用な苦しみの中で人生最後のときを過ごさなければならなくなる可能性が非常に高い。これを避けるためには、本人の覚悟もそうだが、何よりも看取る家族全員が事前に「楽に死なせてあげたい」という強い決意を共有することが不可欠だ。
死んでいく本人が絞り出すような声で「家に帰る」「死なせてくれ」と訴えているのに、配偶者や子、ときには親戚の「最後まで頑張って」「可能な限りの治療を」などという無責任で無慈悲な言葉で拷問が続くケースが多い。
家で死ぬことは、死んでいく本人と看取る家族の共同作業なのだ。
これは簡単なことではない。
死ぬまでにあと1週間、などと期限が区切られていれば、死ぬほうも看取るほうも覚悟を決めやすいが、そうはいかない。余命幾ばくもないなら家で死なせようと病院から家へ戻した途端に状態がよくなって、それから何年も自宅での介護生活が続いたなどという例はたくさんある。
介護に疲れ果てて親や配偶者を殺したり心中したりする事件はたくさん起きているし、これからも急増していくだろう。
考えれば考えるほど、クリアしなければならない問題が多すぎて、今の日本では「家で自然死する」など不可能に近いのではないかと思える。
……とまあ、こんなことを調べていた。
本ではさらに、在宅医療専門医のジレンマや、「ではどうすればいいのか」という具体的な解決案まで書いているのだが、そのへんはできあがるまではヒミツ。
医師が書く「死に方の本」を何冊も読んだが、彼らはとても正直でまともな神経を持っている人たちだと思う。
だが、そういう医師に出逢い、看取ってもらえる人は極めて少ない。
また、医師だから書きづらいこともあるだろう。
だから、医師でも宗教家でもない僕が書く意味を持たせるために、そういうものを全部取り払って、合理的にかつタブーを恐れずに書くつもりだ。
 一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ
一つ前へ |
目次へ
| 次の日記へ