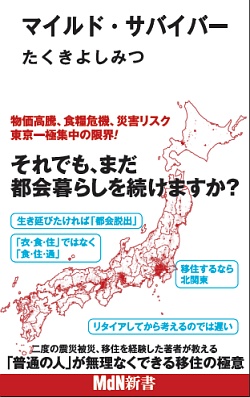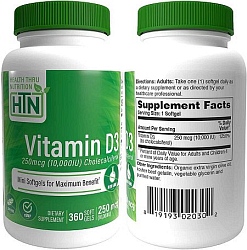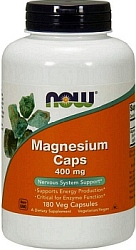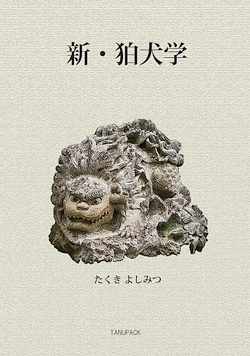天からバッタが降ってきた

バルコニーに出ているのぼるくんを部屋の中に呼び戻そうと窓を開けたら、突然パタンという音とともに上から何かが落ちてきた。
よく見るとバッタさんである。
全身が緑色一色の立派なバッタ。キリギリスっぽいけれど、ちゃんと調べてみるまでは同定はできない。
指を近づけたらまた飛んでいくのだと思ったのだが、動かない。
え? 死んでる?
そっと触ってみると、微かに動く。生きてはいる。
もう寿命なのかな。
そのままにして、部屋に引っ込んだ。夜までには死んでしまうのだろう。
夜になって、外の電灯をつけて見てみたら、同じ場所で腹を上にして動かなくなっていた。死んでしまったのだろう。
寿命なら仕方がない……。
2022/10/28
一夜明け、昨日のバッタさんの死骸を埋めてやろうとしたら……。
え? 起きてる? 夕べは仰向けにひっくり返っていたのに。
風でまた向きが変わっただけかと思ってそっと触れたら、まだ動くではないか。
この世界にまだ未練があるのか……。
よく見るとお尻からイモムシのようなものが出ている。もしかして寄生虫?
で、改めてネットで調べてみると、キリギリスの仲間には違いないが、樹上性で飛翔能力の高いサトクダマキモドキというバッタだと分かった。
なんちゅう名前やねん。
クダマキというくらいで、ブツブツと文句を言うバッタなのか?
実は、江戸時代、「クツワムシ」や「ウマオイ」などは、その鳴声が機織(はたおり)のとき紡車を巻く音に似ていることから "クダマキ(管巻)" と呼ばれていたのですが、それらの大型昆虫に本種が似ていることが命名の理由なのです。
つまり、彼らのモデルとなったのは「クツワムシ」などの昆虫ですが、何故かストレートに「クツワムシモドキ」と名付けられることはなく、“モデル”の“あだ名”に“モドキ”を付ける、という少々変則的なものだったのです…
(大阪府WEBサイトの⇒こちらのPDFより)
本州にはヤマクダマキモドキ、サトクダマキモドキ、ヒメクダマキモドキの3種類がいて、これは平地に棲むサトクダマキモドキ。
ヤマクダマキモドキは標高の高いところにいて、脚が茶色っぽく色がついていることで見分けられるという。
で、これは♀で、お尻から出ているのは産卵管なのだった。ものすごくぶっといな。でも、それもクダマキモドキの特徴の一つらしい。

こんなに太いと、産卵管だとは思わないよなあ

寄生虫にやられているわけではないらしいので、とにかくあとは静かにご臨終を見守ることにした。
クダマキモドキは樹皮を切り裂いてそこに卵を産みつけるそうなので、もし産卵途中なのだとしたらここでは可哀想だと思い、バルコニーにまで伸びてきているヤマボウシの枝を折ってそばに置いた。
このまま死んでしまうにしても、少しでも木の気配があったほうがいいだろうと思って。
夜、またガラス越しに見てみたら、木の枝に絡みつくようにしていた。このまま死んでしまうのだろう。
2022/10/29
3日目に突入。さすがにもう死んでいるだろうと思ったのだが、まだ生きていた。驚くほかない。

産卵管が異常に太く、飛び出しているのは、産卵途中で卵がうまく出てこなかったのだろうか。
しかし、今から卵を産むとも思えないので、土と木の枝、枯れ草のある場所に移した。
ヤマボウシの枝も横に挿しておいた。
成虫の姿で越冬する昆虫は数少ない。でも、こうして生きただけでもよかったね。
晩秋の哀歌というか、なんか今の自分の姿にも重ねてしまうのだった。
↑まとめ動画作ったので見てね
2022/10/30
4日目。ついにご臨終。空から降ってきて、我が家のバルコニーに数日滞在し、肉体を離れて点に戻って行ったか……。合掌
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ