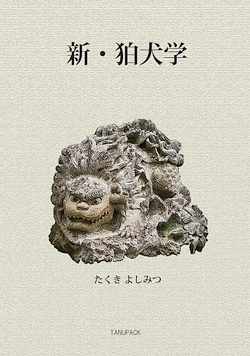次はすぐそばの温泉神社。
ここの神社の狛犬はGoogleマップの写真で見る限り、野田平業ではないかと思えたのでチェックしたい。
平業は実に多作な石工で、私が把握しているだけでもざっとこれだけの狛犬を彫っている。
↓
野田平業 作品リスト 明治31(1898)年10月6日~昭和56(1981)年10月23日(83歳)
- 八幡神社 白河市関辺大久保 大正5(1916)年10月 彫刻師白河横町 野田豊吉
- 愛宕神社 福島市飯坂町湯野愛宕山公園内 年代不明 磐城白河之住 彫工 野田平業作
- 南湖神社 白河市菅生館 大正11(1922年)年10月 野田平業謹刻
- 八幡神社 福島市八島田東本庄町 大正12(1923年)年
- 八島田八幡神社 福島市八島田字北古屋6-1 大正12(1923年)年春1月 磐白白河 彫刻師野田平業
- 秋葉神社 棚倉町北町 大正13(1924年)年8月5日 白河之住 彫刻師 野田平業刻 台座石工 白山正平
- 羽黒神社 白河市表郷番沢字御殿ケ入 大正13(1924年)年10月
- 永倉神社 西白河郡西郷村長沢字長沢 大正13(1924年)年12月 野田豊吉
- 三島神社 棚倉町山際字屋敷前 大正15(1926年)年旧11月16日 白河之住 彫刻師野田平業
- 日吉神社 矢吹町大和内 大正15(1926年)年 白河町 彫刻師野田平業作 台石に野田豊吉 白河町 台石 石工 根本末吉)
- 熊野神社 東白川郡塙町豊田 大正15(1926年)年
- 宇迦神社 棚倉町棚倉字風呂ケ沢 昭和2(1927)年 白河町野田平業彫刻 台座工事 棚倉町石工 藤田亀治
- 八幡神社 鮫川村赤坂中野 建立年不明
- 羽黒神社 棚倉町堤字羽黒東 昭和3(1928)年11月10日 白河町横町 野田豊吉 奉納御大典記念
- 都々古別神社奥社 白河市表郷三森 昭和3(1928)年11月10日 彫刻師 白河之住 野田平業作 御大典記念奉献
- 白山神社 棚倉町流字東山 昭和3(1928)年11月10日 磐城白河之住 彫刻師野田平業 御大典記念
- 鹿島神社 白河市大鹿島 昭和4(1929)年1月吉日 野田平業 彫刻師白河横町
- 熊野神社 泉崎村 昭和4(1929)年1月 推定
- 都々古別神社 白河市表郷梁森石崎 昭和9(1934)年10月17日 白河町彫刻師野田平業作
- 熊野神社 白河市表郷 昭和9(1934)年 銘なし推定
- 近津神社 棚倉町山田字芳ノ木 昭和11(1936)年10月9日 白河横町之住 彫刻師野田平業作
- 住吉神社 棚倉町岡田字入沢 昭和12(1937)年10月9日 銘なしだが平業であろう
- 稲荷神社 小野町 昭和12(1937)年9月 狐 白河町字横町之住 彫刻師 野田平業作
- 諏訪神社 川内村
- 三島神社 南相馬市原町区本町1-1 昭和13(1938)年旧正月 白河町之住 彫刻師 野田平業作
- 八幡神社 矢吹町八幡町 昭和15(1940)年3月15日 白河町横町 野田平業作
- 諏訪神社 白河市飯沢 昭和15(1940)年 野田豊吉
- 矢吹神社 矢吹町中町 昭和15(1940)年
- 乃木神社 那須塩原市 昭和15(1940)年 白河横町之彫刻師野田平業作 台座石工渡辺末吉の名
- 川崎宮八幡神社 二本松市 昭和15(1940)年 磐城白河町之住 彫刻師 野田平業作
- 賀茂神社 さくら市 昭和15(1940)年10月13日 白河町字横町 彫刻師 野田平業作
- 宇佐神社(八幡宮) 滝根町 昭和15(1940)年 皇紀2600年もの 石工・大堀末吉 となっているが、どう見ても平業?
- 薄葉温泉神社 大田原市蛭田 昭和16(1941)年6月 皇紀2601年 白河市横町彫刻師野田平業作
- 川辺八幡神社 玉川村川辺 昭和17(1942)年 野田平業 石工小針岩晴 参宮記念
- 苕(くさ)野神社 双葉郡浪江町請戸 昭和17(1942)年2月28日 彫刻師野田平業作 白河市字横町之住 台座 石工 今福栄蔵
- 八幡神社 棚倉町逆川字前山 昭和17(1942)年7月7日 野田平業 大東亜戦完捷祈願 野田平業
- 御霊神社 棚倉町下手沢字水沢 昭和26(1951)年9月9日 講和記念 白河市横町之住 彫刻師野田平業 台座工事 棚倉五十嵐石材工業
- 薄葉温泉神社 大田原市 昭和29(1954)年 白河市横町之住 彫刻師野田平業作 56歳?
- 福満虚空蔵尊 圓蔵寺(柳津)
- 大甕倭文神社 茨城県日立市 ?
- 佐波波地祇神社 (さわわちぎじんじゃ・さははくにつかみじんじゃ)茨城県北茨城市 ?
- 瀬縫不動 那須町高久 ?
……実に40対を超えている。
生涯の間にこれだけの数の狛犬を彫れる石工は他にいないだろう。技術がどうのという以前に、これほどの数の受注があったことが不思議でならない。
平業は自己顕示欲の強い人で、多くの狛犬には「彫刻師 野田平業」という銘を入れているが、台座には請け負った石屋の棟梁の名前が彫られることが多いので、台座の石工名があてにならない。
宇迦神社の狛犬がよい例で、台座には大きく石屋の棟梁の名前が彫られており、平業の名は狛犬のすぐ下の平たい台石脇に小さく彫り込まれている。
若い頃のいくつかを除き、すべて同じ顔なので、パッと見ただけで「あ、平業かな?」と分かる作風。
この温泉神社の狛犬もまさしくそれだった。
しかし、石工名はどこにも見あたらなかった。
昭和19(1944)年4月とあるので、平業であれば、上のリストにあてはめると、
八幡神社(棚倉町逆川) 昭和17(1942)年7月7日
と、
御霊神社(棚倉町下手沢) 昭和26(1951)年9月9日
の間に入る。
太平洋戦争開戦後、戦時中に彫られた狛犬としては最後のものであり、終戦後は昭和26(1951)年9月に「講和記念」と彫られた狛犬まで6年空いている。
戦時中最後の作と推定されるので、平業の狛犬人生にとって、かなり意味のある作ではないだろうか。

こんな感じの神社。道路のすぐ脇に位置していて、クルマも停めやすい。

石段を登ると正面にど~んといた。


台座の感じも含めて、一目で「平業かな」と思う佇まい。





これはもう完全に平業だろう。顔を見て確信した。

鬣などを深く細かく彫り込んでいるのも平業の作風。間違いないだろう。


吽像には子獅子がいる。



吽像の尾。

阿像の尾。

阿像は籠彫りの玉を持っていたが、籠彫りが壊れてしまっている。

「大東亜戦争戦勝祈願 霊忠 昭和十九年四月二十九日」 とある。

吽像の台座は「報国」。

「○○戦」「○○事変」「戦捷」「戦勝」などはよく見るのだが、「戦争」という文字を初めて見たかもしれない。現代人にはインパクトがある。

奉納者の名前はズラッとあるのだが、石工名は見つからなかった。時期的に、平業としては名前を入れるのをためらったのかもしれない。
平業の作品リストに加えてもいいだろう。
お孫さんの話では、平業は終戦後はほとんど仕事を請けなくなって、数作しか彫っていないという。やはり戦争を見てきたことで気持ちに大きな変化が訪れたのだろう。
戦時中最後に請けた仕事がこれで、台座には「戦争戦勝祈願」と彫られている、というあたりに、狛犬史としても貴重な資料となる作品だと思える。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ