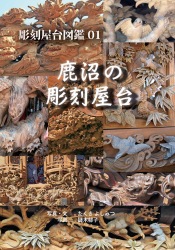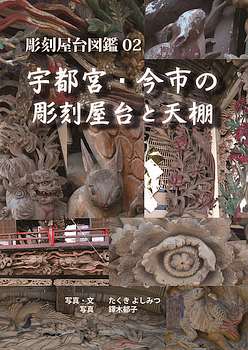内蹴込

内蹴込部分の彫刻がとても面白い。(赤く囲んだ部分)

波間で鳥が鯛を捕まえていて……

その後方でも、波に見え隠れしている魚を鳥が狙っている。

ガッチャ! あ~!

あ、あいつ食われたわ~
内欄間

内欄間は松と鷹かな。


鳳凰っぽくも見えるけど、松と組み合わせているから鷹なんだろう。

脇障子裏側


脇障子の裏側も目に触れる部分なので、ちゃんと彫り込んでいる。

前欄間

前欄間もなかなか見づらいのだが……

鶴かな?

餌を受け渡している?

後欄間

後欄間は鳳凰かな。よく見ると後ろに小振りのがいて、親子?


作者は誰なのか?

天井を見ると、棟木に建設の年月日が書かれているようだが、ちょうど年号部分が隠れて見えない。


収蔵庫建設設計を担当した佐々木設計さんのブログに、全部写っている写真があった。明治15(1882)年のようだ。
文挾屋台の制作年は、文化文政時代説と明治15(1882)年説があって、日光市のサイトにもそう書かれているが、棟木に書かれている年月が正しいのだろう。明治15(1882)年に屋台本体のみ補修して作り直したという可能性も残るが、彫刻も全部きれいな状態で残っているので、明治15(1882)年で間違いないだろう。
では、彫刻師は誰か。
彫刻の作風からして、磯辺系の彫り師には間違いないはず。明治15(1882)年に生きていたのだから、磯辺儀兵衛松需敬信(1830-1897)だろうか。
神山政五郎(1808-1892)も時代としては該当する。
敬信の彫った屋台は鹿沼の天神町の屋台がある。

↑天神町の屋台。脇障子。龍虎の意匠も作風も同じ。

↑天神町の屋台。後方鬼板。
政五郎の彫った屋台としては今市の春日町2丁目の屋台がある。

↑春日町二丁目の屋台。脇障子の龍虎。これも同じ。

↑春日町二丁目の屋台。高覧下の鯱と波の彫り方も同じ。
磯辺敬信なら52歳のとき、神山政五郎なら74歳のとき。
どちらもよく似ているが、強いていえば政五郎のほうが作風は近いだろうか。現代の名工・黒崎嘉門さんも政五郎ではないかと考えているようだ。
しかし、明治時代、74歳でこれだけ勢いのある彫刻をしていたのだろうか?
政五郎の弟子・大出常吉かもしれない。大出常吉は嘉永2(1849)年に今市瀬川に生まれているので、明治15(1882)年には30代前半だ。
今市の相生町、春日町二丁目の屋台も政五郎と常吉の二人で彫っているようなので、常吉の線が濃厚だろう。
感じるのは、この文挾の屋台の彫刻群は素直で「迷いがない」ということだ。
極めて優秀な弟子(常吉?)が師匠の技術を見事に継承してサクサクと彫ったのか……。
ちなみに、大出常吉の師匠・神山政五郎(文化5(1808)年~明治25(1892)年)の師匠は石塚直吉知興(田沼宿生。鹿沼に移住)で、その師匠が初代・磯辺儀兵衛(隆顕)(?~文政4(1821)年)。
初代儀兵衛は三男で、父親は磯辺家初代の磯辺儀左衛門(信秀)。
信秀は刀工で、上州沼田から富田宿(現栃木市)に移住した。刀工の傍ら、結城の竹田藤重郎に師事して木彫も学んだという。
その竹田藤重郎の師匠は斉藤八郎兵衛といい、その師匠は「公儀彫物師」を拝命し、上州の彫り師集団の祖とも呼ばれる高松又八(上州花輸村生)。
その師匠が江戸で名彫工と呼ばれた島村俊元。その系譜のもとには左甚五郎がいて日光東照宮の彫り師集団へとつながっていくらしい。
いずれにせよ、江戸時代から脈々と継承されてきた彫師たちの技術の素晴らしさを示している。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ