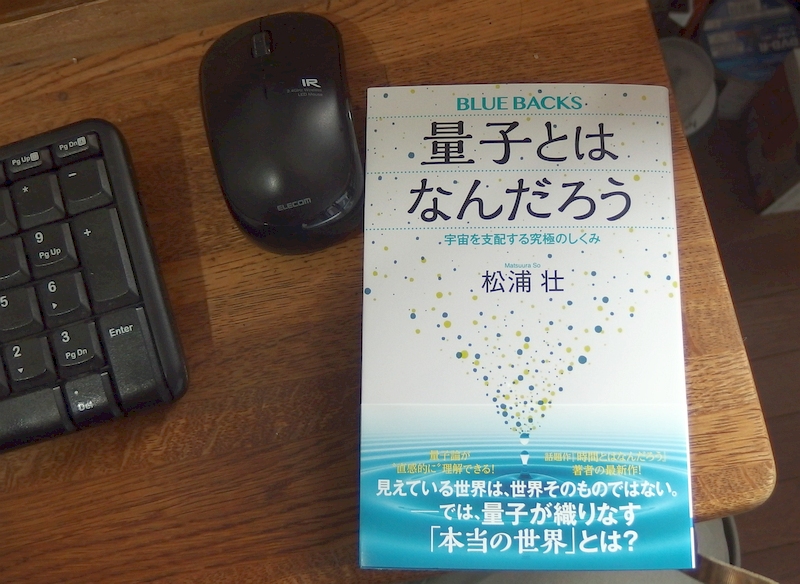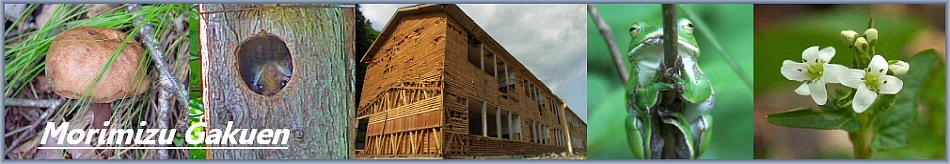ここにも亨保年間の如意輪観音が

郵便局にご注文の本を出しに行った帰り、坂道の途中にある、いつも素通りしてしまう墓地に立ち寄る。
ここにも亨保年間の如意輪観音がいた。新しく整備された墓地に並ぶ墓石群を指揮しているみたいに向かい合っているのが面白い。

享保15(1730年)年。290年前。


右側の文字はなかなか読めなかったが「紅禅定尼」ではないかと「こまさが隊」の副隊長が「心眼」?で読み切る。確かに「紅」と「尼」は読める。「尼」とあるので戒名だなということは分かった。つまりこれは「墓」なのだ。女人講が建てたものとは性格が違うが、同じ時代である。

墓地の外れにポツンと立つ地蔵菩薩。新しいものかと思ったが……

享保十年(乙巳)だった。1725年だから295年前。手前の如意輪観音より古かった。

それにしてもこの配置……何か意図があるのだろうか。無縁仏なので、墓地内には一緒に置かないということなのかな。
リアル案山子

そのそばの農家。あの人、動かないなあと思ったら……案山子だった。

量子論にはまるかも?
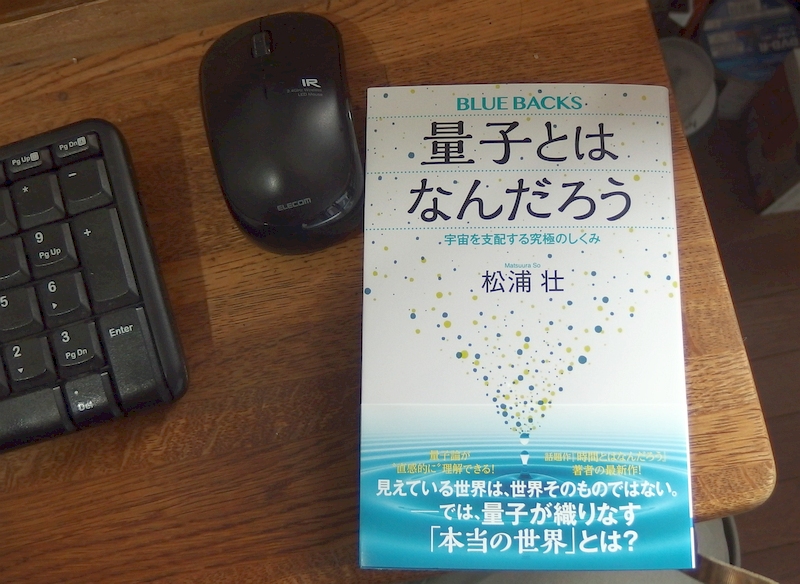
「量子が支える宇宙の本質」というPR文を読んで、ホイホイと購入した本。
「はじめに」の部分は期待しながら読めたのだが、中身は難しかった。数式がバンバン出てくるあたりで息切れ。
なお、この本ではできる限り言葉による説明を心がけますが、正しい経験を積むために必要な数学は敢えて避けません。(略)とはいっても、計算自体は中学生でもわかるレベルなのでご安心ください。(「はじめに」より)
……というのだが、中学生レベルで行列の数式なんか出てくるの? 今の教育って?
しかし、「言葉による説明」の中にはいくつもハッとさせられる表現、記述があって、老化が激しい私の脳みそでも、何度も読み返すことで私なりの「直感」「想像力」が刺激され、整理される可能性も感じた。
ただ、ほんとに大変で、数ページ読むとどっと疲れてしまい、ベッドに横になる……の連続だった。
夢の中にも出てきて、未明に「ああ、こういう風に書けばいいのかな……」という考えが頭の中を駆け巡るのだが、起きていつもの1日が始まると、何を思っていたのか忘れている。
漠然と今感じているのは、肉体が朽ちてしまってもどうということはないと思えるようになれば、残りの時間(この「残りの時間」という考え方そのものも錯覚なのかもしれないが)を少しでも楽しく過ごせるかもしれない、というようなこと。
数学の得意な小中学生には理解できなくても、哲学や芸術に興味を持っている中高年には少しは刺激的な娯楽を与えられるような文章に昇華できないか、挑戦してみる価値はあるかもね。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ