
2019/11/20
秩父の観音院へ仁王像を見に行く(7)

もう一か所だけ。手前にある「たらちね観音」というのがちょっと気になったので寄ってみた。来る途中横を見たらネコがのんびりしていたのだが、もう暗くなってきたのでネコも人もいない。
暗い拝観所に登って、お顔を拝ませていただいた。


真っ暗闇に近いので、こんな感じにしか撮れなかった。



飾り気のない、オープンな雰囲気の場所だった。

というわけで、今回の遠征はここで終了。帰りは高速を使って帰宅。
あとから調べたら、観音院からそう遠くない場所にある龍頭神社に、吉弥が作った燈籠があって、それを支えている力鬼が可愛らしいという情報が……。
あ~、これは前に調べて知っていたのだが、すっかり忘れてしまっていた。残念。
しかし、藤森吉弥や黒沢三重郎の人生に思いをはせるよい小旅行だった。
仏教美術にとって「失われた20年」とも言える明治前期を、吉弥や三重郎はどんな思いで過ごしていたのか。
吉弥が狛犬を彫っていたら、どんな作品になったのだろう。
もしかしたら、知られていないだけで、どこかにあるのか……。
う~ん、多分、狛犬にはあまり興味がなかったのかもしれないな。そんな気がする。
信州伊那地方には狛犬文化は花開かなかった。だから高遠石工が残した狛犬というのはほとんどない。修業時代に狛犬というものに触れていないのだろう。
だから、旅先で「狛犬を彫ってくれ」という依頼を受けたときは困惑したのではないか。仏像なら彫れるが、狛犬なんて彫ったことがないし、知識もない。
結果として、江戸風でも浪花風でも出雲型でもない、はじめ狛犬に近いようなものを彫る。でも、技術のある高遠石工だから、村石工が彫るはじめ狛犬とはレベルが違う出来になる。
……そんな気がする。
彫った狛犬に対して、高遠石工たちはあまり自信が持てなかったのではないか。それで銘も残さなかった。だから、「高遠石工が彫った」とはっきり分かる狛犬はほとんどない。
それなのに、利平はあれだけすごい狛犬を彫って、福島の地に高度な狛犬美術の花を咲かせる種を蒔いた。小松利平は、本当に不思議な石工だ。
小説・神の鑿 ─高遠石工・小松利平の生涯─
「神の鑿」石工三代記の祖・小松利平の生涯を小説化。江戸末期~明治にかけての激動期を、石工や百姓たち「庶民」はどう生き抜いたのか? 守屋貞治、渋谷藤兵衛、藤森吉弥ら、実在の高遠石工や、修那羅大天武こと望月留次郎、白河藩最後の藩主で江戸老中だった阿部正外らも登場。いわゆる「司馬史観」「明治礼賛」に対する「庶民の目から見た反論」としての試みも。
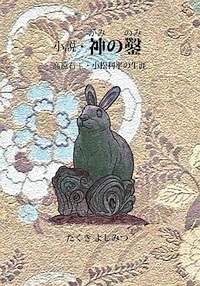


Kindle版は643円。(Kindle Unlimitedなら0円)
 ⇒こちら
⇒こちら


 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ

『神の鑿』『狛犬ガイドブック』『日本狛犬図鑑』など、狛犬の本は狛犬ネット売店で⇒こちらです
更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報


 books
books
 music
music
 目次
目次
 HOME
HOME
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ










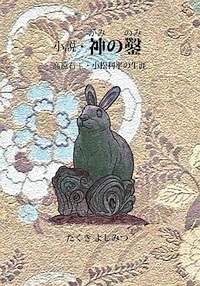



 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ