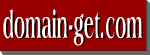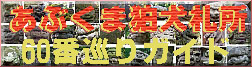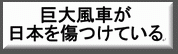2013/02/04の2
人の営み(承前)


このへんに家を建てると、遠くに日光連山が毎日見えている感じかな?↑






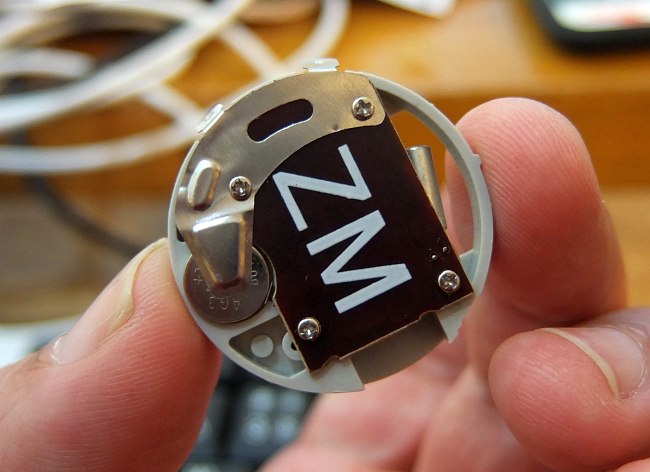
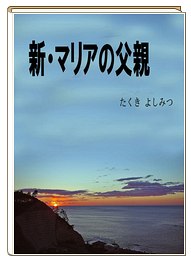
|
 第四回「小説すばる新人賞」受賞作。改訂新版としてデジタル書籍で復活。 ◆横書きKindleバージョン(Kindle端末、iPhone、iPod touch、iPadなどのKindleソフトで読む場合に推奨)⇒こちら ◆縦書きバージョン(iBooksやKindleなどで縦書きで読みたい場合はePub版。PDFをPCで読む場合はPDF版をDL)⇒こちら ◆楽天kobo で購入の場合は⇒こちら ◆その他、アマゾン Kindleストアでのたくき作品購入は⇒こちら |
|---|
|
|
|---|














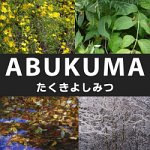
|
 『ABUKUMA』(全11曲)
『ABUKUMA』(全11曲)7年間過ごした阿武隈に捧げる自選曲集。全曲リマスター。一部リミックス。新録音『カムナの調合』弾き語りバージョンも収録。 アマゾンMP3、iTunesストア、キメラなどから販売中。 ⇒こちらからどうぞ ⇒ライナーノートはこちら |
|---|
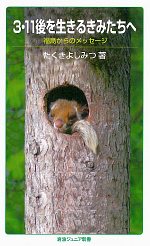
|
『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ) 『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言 第1章 あの日何が起きたのか 第2章 日本は放射能汚染国家になった 第3章 壊されたコミュニティ 第4章 原子力の正体 第5章 放射能より怖いもの 第6章 エネルギー問題の嘘と真実 第7章 3・11後の日本を生きる ■今すぐご注文できます ⇒立ち読み版はこちら |
|---|
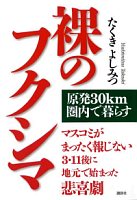
|
『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ) ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。 第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか? 第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実 第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった 第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様 第5章 裸のフクシマ かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛 ■今すぐご注文できます ⇒立ち読み版はこちら |
|---|
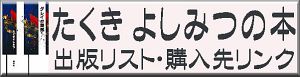

 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ