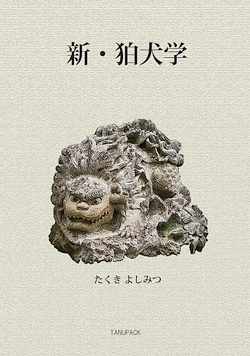2021/11/27
今日のコナラ
2021/11/28
クイーンズ駅伝
待ちに待った(大袈裟か)クイーンズ駅伝。
出走表(競馬じゃない)を見ての事前予想では、優勝は積水化学だろうなぁ。あと、資生堂が強そうだ、日本郵政は鍋島が抜けているし、廣中璃梨佳だけじゃ優勝は無理っぽいなと。
予想通りになってしまい、ちょっと拍子抜けしたが、みんなしっかり走りきって、いいレースだった。

勝負の5区。中継所で「もう帰る」とごねる新谷をいつものようになだめすかす横田コーチ。その後ろで、この後激走するりのりんは平常心で待つ。
りのりんは新谷姉御を1秒上回る劇走で、まさかまさかの区間賞。すごい成長ぶりだ。日光いろは坂駅伝で1区をぶっちぎって走る姿を生で見て以来、ずっと応援してきたのだが、こんなに早く日本のトップクラスに追いつくとは思わなかった。それなのにメディアはりのりんのことはほとんど触れずに、新谷と璃梨佳ばかり。そういうとこだよ、日本の陸上界をダメにしているのは。

あたし的にはMVPはりのりんにあげたい。敢闘賞はさやさや #佐藤早也伽 、なるぱー #佐藤成葉 。新人賞は ななっしー #木村梨七 かな。みんな頑張った。さわやかなレースだった。
のぞき窓ごしのにらみ合い

妙にきれいな茶虎が来ている。毛がボロボロだったチャーとは別猫みたいだ。チャーはまったく姿を見せなくなったが、死んでしまったのだろうか。
2021/11/30
狛犬の精神史
このところ考えているのは「狛犬の精神史」というテーマで何か書けないか、ということ。
狛犬を仏像や建造物のように「もの」「美術品」としてだけ考えていると、何か大きな落とし穴があるような気がする。
平安時代、鎌倉時代の木造狛犬と江戸時代の石造狛犬はまったく違うものなのではないか。同じ「狛犬」という言葉でひとくくりにしているから、造形による分類とか、素材による分類とかという方向にどんどん傾倒していく。
奈良~平安時代の文化は仏教美術を基本にした公家文化だった。
木造の狛犬は、貴族が中国文化を真似て生みだした公家文化の中で生まれたものだ。仏像彫刻に付随する美術、装飾品のような位置であり、それを生みだした精神的背景はあくまでも仏教文化であろう。
その意味では、奈良・平安・鎌倉時代の木造狛犬は、特別なものではなく、中国文化の延長のようなものだ。
一方、武力による貴族の権力闘争が続くと、戦いを手段とした武士というグループが力を持つようになる。血統による身分保障を武力で破壊し、成り上がる精神が基本である武家社会では、それまでの貴族のような教養や美的なセンス、たしなみといったものに耽る余裕はない。むしろそうした精神は軟弱で情けないものだという認識がある。
しかし、武家社会の中にも、自らの力の証明として寺社を建立したり、寺社に祭られた神に武運を祈ったりする精神性を尊ぶ者は多くいた。
そうした武家社会から、やがて貴族的な文化を愛する者も出てくる。
有名な大宝神社の狛犬は、台座の裏に「伊布岐里惣中」という墨書きがあるという。
「惣」は、中世後期から出てきた村の自治組織で、荘園時代からの領主に対して村民が談判したり、村の結束を固めるために作った寄り合い組織のことで、次第に武士化していく。
つまり、あの狛犬は、公家ではなく、武家社会に入りたがっていた庶民のグループが奉納している。木造ではあるが、それまでの木造狛犬とはかなり違う雰囲気なのは、そうした背景があったからではないか。
一方、武家社会で成功を収めた殿様たちの中にも、公家的な文化に憧れ、自分も武力だけではない、教養のある人間なのだと主張したがる者たちが出てくる。
室町幕府三代将軍・足利義満などは極めて公家的な人物だったと思われる。
徳川三代将軍・徳川家光もそうだ。どちらも金ピカ趣味なのが共通していて、そのへんがちょっと……ね。でも、美術家のパトロンとしての役割は大いに果たしたといえるかな。
家光の時代、それまでの「公家狛犬」とはかなり趣が違う「武家狛犬」とでも呼べそうな石像の狛犬が生まれ、その後の狛犬奉納ブームにつながっていったのではないか。
……と、まだ考えがバラバラなのだが、そうした思索を結びつけていくと、同じ「狛犬」という言葉でひとくくりにされているものが、実はかなり違う精神性を持って生まれてきたのではないかという論考をまとめられないか、と考えている。
さらには、文字による伝承、表明ができなかった庶民文化の精神性を、狛犬という後世にまで残された形のあるものが教えてくれるのではないか……。
文化や文明を考える上では、そうした形として見えにくい「精神性」を想像することが大切なのではないか、という気がしている。
そんなわけで、最初は「狛犬の近現代史」というタイトルを考えていたのだが、もう少し遡ってもいいかなと思うので「精神史」にしようかな、というわけだ。
77年という時間
狛犬の精神史を考えていく上でも、近現代史全般をしっかり学び直さないといけないなと思っている。
特に「虐殺の近現代史」という視点で見つめ直している。
11月11日の日記にも書いたが、ある時代に大量の人が理不尽に殺されたり見殺しにされたりする背景には、サイコパス気質の権力者の他に、自己中心で無責任・無能な権力者や、それを支持する(あるいは黙認し、同調圧力に負けて動かされる)大衆という要素も存在する。
戊辰戦争から太平洋戦争敗戦まで77年だが、この77年間は理不尽な大量死が続く時代だった。
- 1868 戊辰戦争
- 1874 佐賀の乱、台湾出兵
- 1877 西南戦争(死者約1万2000人)
- 1878 大久保利通暗殺、竹橋事件(陸軍近衛兵部隊による武装反乱)
- 1879 コレラ大流行(死者10万人超)
- 1882 朝鮮半島で壬午軍乱
- 1884 朝鮮半島で甲申事変
- 1894 日清戦争
- 1895 三国干渉、閔妃(びんひ:李氏朝鮮の第26代王・高宗の妃)殺害
- 1900 義和団の乱(制圧した欧米列強連合軍の半数近くは日本軍)、山縣有朋による軍部大臣現役武官制
- 1902 八甲田山死の行軍、日英同盟締結
- 1904 日露戦争 (日清・日露戦争を通じ、脚気で死んだ兵士は3万人を超える。白米主義に固執した陸軍がほどんどで、麦飯に切り替えた海軍での死者はほとんどいない)
- 1910 大逆事件(社会主義者を弾圧・死刑に)
- 1912 明治天皇崩御、乃木対象夫妻の殉死
------------------------ここまでが明治----------------------------
- 1914 第一次世界大戦
- 1918 米騒動。シベリア出兵(欧米列強の撤兵後も日本は駐留を続けて日ソ、日米関係が悪化)。スペイン風邪世界的な流行
- 1919 朝鮮で三一独立運動起こる
- 1923 関東大震災(死者10万人超)
- 1925 治安維持法。普通選挙法(25歳以上の男子)
- 1926 12月25日、大正天皇崩御
---------------------ここまでが大正-------------------------------
- 1929 世界恐慌
- 1931 満州事変(満州のほぼ全域を日本軍が占領)
- 1932 満州国建国(日本の世界的孤立が始まる)。5.15事件(海軍の青年将校が犬養毅暗殺)
- 1933 国際連盟脱退
- 1936 2.26事件(陸軍の青年将校が要人を襲撃)
- 1937 盧溝橋事件~日中戦争(1945まで続く)。南京事件
- 1938 国家総動員法(戦争目的なら国が人的物的資産を自由にできる)
- 1940 日独伊三国同盟
- 1941 真珠湾攻撃→太平洋戦争開戦
- 1944 昭和東南海地震
- 1945 東京大空襲、沖縄戦、原爆投下~降伏 (日中戦争後の日本人死者数は約310万人。総人口の約3割とされる)
この敗戦から現在までが同じ77年だ。
同じ77年間なのに、日本は奇跡的に戦争に直接巻き込まれずにきた。世界的にも稀なケースだ。
私は敗戦の年の10年後に生まれたので、もうすぐ67歳になる。さらに10年生きれば77歳だが、はたしてこの10年を今までのように平穏なまま生きられるのだろうか?
戦争やテロのような物理的暴力も怖いが、同調圧力による精神的分断や迫害が過熱する社会、さらには生物化学的な外力に巻き込まれてあっという間に環境が変化することも怖い。
それはすでに進行している。近現代史を学ぶと、そうした社会の流れは変えられないだろうという諦観に包まれてしまう。
押しつぶされぬよう、うまく自分の精神をコントロールしなくては……。
年末状を入稿したら、あっという間に印刷されて発送の通知が来た。
年末状というのは喪中葉書のことではない。喪中に関係なく、私たちは生きてますよ、とお知らせするご挨拶状のようなもの。「おめでとう」とか「謹賀」とか書いてないので、喪中の家に届いても問題ないだろう、ということで、だいぶ前から年賀状はやめて「タヌパック短信」というタイトルの年末状にしている。
喪中葉書といえば、今年は今のところは6通来ている。30人に1件くらいの割合。結構多い。まあ、自分たちも高齢者なので、当然、毎年そういうのが増えていくのだろう。
当人が亡くなってしまえば、喪中葉書も来なくなる。
そういうケースも、今年は結構ある。
寂しい。
干し柿その後

かなり食えそうな感じになってきた。1つ試しに食ってみようか、それとももう少し待つか……
柿の木に生った実はまだ鳥が食べに来ない。ということは、もう少し待ったほうがいいのかな。
2021/12/01
いよいよ本格的に散り始めた。しばらくは大変だ。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ