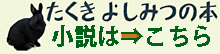テレビを見ていると、しょっちゅうお肉だのなんだの、食材が大写しされる。
高級和牛の肉塊とかが映され、タレントが異口同音に「おいしそ~」とかいうシーンを見て、助手さん曰く、
「こういうのは日本人の
種の記憶にはない」
「種の記憶」かぁ……確かに。
大昔、日本では牛の肉を食ってはいなかったはず。猪とか鹿とかはあったかもしれないけれど。
「種の記憶」をネットで検索すると、日本人作家が書いた小説?がズラッとヒットする。
いや、哲学の話で……と、さらに広げて検索すると、ベルクソンの『物質と記憶』とか、スティグレールの『偶有(アクシデント)からの哲学―技術と記憶と意識の話』なんていうのがようやく引っかかってくる。




『偶有(アクシデント)からの哲学』の解説文が非常に興味深かった。
人類は個体の記憶(経験)と種の記憶(遺伝)に加えて第三の記憶、つまりモノの形をとった個体の経験の蓄積である文化を持つ。後成的でありかつ、子孫に伝えられるという意味で種レベルのプロセスでもある「後成的系統発生」が、「ヒト」を「人類」たらしめ、その独自の歩みを支えてきた。何か(有形無形を問わず)を作る術=技術は人類史上欠かせない要素なのだが、哲学は一貫してその重要性を等閑視し否認してきたのである。
ところが産業革命を経て産業がヘゲモニーを握って以降、記憶をめぐって新たな状況が生じる。蓄音機と映画は過去の正確な再現を可能にするが、一方で、同じ音楽や映像(時間の流れと共にのみ存在する時間的対象)が大規模に流布することにより、人々の意識が同じ時間を生きる「シンクロニゼーション」の傾向が生まれる。
いまや文化産業は、人間の「意識の時間」を開発=搾取の対象とする。また、種の記憶たる遺伝子に対する操作も考え合わせれば、現代ではあらゆる意味での記憶が、各種産業にとっての原材料となりうるのだ。この状況において、哲学は、科学は、産業は、そして市民は何を考えるべきか…。今最も注目される哲学者の一人スティグレールが縦横に語る。
(浅井幸夫 上智大学教員/フランス文学)
なんか、難解ホークスなので、ここは野村監督に簡単な言葉でボソッと呟いてもらおうか。後半部分をね。
蓄音機や映写機の発明で、わしらは同じ音楽やら映画やらの体験を大規模に共有できるようになったやろ。
これが「同時代性」ちゅう感覚を生むわけやな。
そうなると、頭のええ連中が、その「同時代的共感」いうもんを商品として売ったり、うまくわしらの脳に刷り込ませることで儲けたり、思考を支配したりするようになるんやな。
……そういうことなのだな。
音楽とは言語である
ついでにもう一つ。最近、気になった本がこれ。
『西洋音楽の正体 調と和声の不思議を探る』 (伊藤友計 ・著、講談社選書メチエ)


この解説文にもちょっと興味を引かれた。
音階や半音の発見、音を重ねることへの傾きと和音原理の探究、長調・短調の整序と規則の整理、また、人間的感情の美的表現から心地よさの追求へ。
西洋音楽は、一つの「世界創造」であった。本書では、その楽理の由来、実践の発展を訪ね、自然と音楽の関係、背景にある思想の展開に焦点を当てる。
西洋音楽とは普遍性を持つものなのか。自然のなかにドレミファソラシドはあるのか。
本の内容は読んでいないので分からないが、この解説文を書いた人の理解力とセンスには脱帽する(著者ではないと思うのだが)。
メロディとはなんぞや、音楽の価値とはなんぞや、という疑問をずっと抱き続けながらも、音楽を創り出すことに自分の人生でいちばんの価値を見出そうとしてきた私としては、無視できないテーマがいっぱい詰まっていそうだ。
Kindle版は期間限定でポイント還元で実質935円か……ちょっと悩むなあ。
ポチしてみるかなあ……どうせ長くない人生だし。
……(ポチしちゃった)……
今まで何度も書いてきたことだが、私は
メロディは文章のようなものだと思っている。
ヒトラーの演説を聴いて(見て)も、ドイツ語が分からない日本人は内容が分からない。ただ、声に張りがあるなあ、とか、この声の質が好きだとか嫌いだとか、ちょび髭がかっこいいとか悪いとか、着ている服がなんとなくカッコいいとかダサいとか、話している内容とは別の要素しか伝わってこない。
音楽も同じで、メロディを文章のように意味のあるものとして感じ取れなければ、音がきれいだとか、聴いているとなんとなく心が落ち着くとか気持ちがいいとか、演奏している姿がカッコいいとか、歌声が好きだとか、あるいは歌であれば、歌詞の内容を自分の今の状況や体験にあてはめて涙が出たとか、そういう感じ方をしてしまうだろう。
私にとっては音楽の価値の9割はメロディの価値だ。
どんな音楽に接しても、まずメロディを聴き取ってしまう。意識してそうしているのではなく、自然と頭の中にメロディが入ってくる。
太鼓の音を聴いても、それが12音階にほぼあてはまっている音であれば「メロディ」として聞こえる。
これは世間でよくいう「絶対音感」とは違う。12音階を使った長音階、短音階にあてはめたドレミファでラベリングできるメロディ、ということにすぎない。このメロディに対する音感が、幼少期に形成された単純なドレミファ音感である、というところが、どうも
多くの人とは異なるらしいのだ。
ジャズのフレーズがカッコいいと感じたり、ボサノバのリズムに新鮮さを感じるのも、自分の音感の基本が単純なドレミファ音階(による西洋音楽)だから、なのだろう。
こんな音の並びがあったのか、カッコいいじゃん、とか、2拍目4拍目を強く弾く奏法ってお洒落~、と感じるのも、ベースになっているのが単純な西洋音楽のメロディだからそう感じる。生まれたときからブルーノートやボサノバのリズムで育った人は、また違う感じ方をするに違いない。
12音階平均律というのは特殊な理論であって、普遍的なものではない。この音階に根ざした音感もまた、特殊なものといえる。
芸人がやっている歌ネタなどで、音程が狂っているのが気持ち悪くてしょうがないと感じるのもまた、特殊な感覚なのだろう。
本来、音楽には様々なスタイル、様式があり、音階があるようでない音楽、歌っている(演奏している)うちに音程が螺旋のように少しずつズレていく音楽、というのもあるはずだ。芸人が歌う歌が平均律12音階からズレていくのも、「演奏しているうちに音程はズレていくのがあたりまえ」というスタイルの音楽だと思えば、ごく自然なものであって、唾棄されるようなことではないのかもしれない。
となると、今、自分が「価値のある音楽」と感じている音楽を一緒に楽しみ、感動してくれる人たちが大勢いる世界というのは、社会(音楽教育や娯楽産業の形)が再構築され、私が持っている音感に近い価値観を持つ人が大多数になる社会が訪れない限り、未来永劫ありえないことになる。
少なくとも、自分が生きている間にはありえないだろうし、死んでからも最低100年は可能性がないだろう。若冲は「私の芸術はあと1000年は理解されないだろう」と言っていたそうだが(ほんまかいな)、1000年先となれば、人間社会が存在しているかどうかも怪しい。石油文明は終わっているはずだし。
そうなると「人生死んだ後が勝負」と思って作曲しているのも虚しい。
だいぶ前にそのことに気がついてからは、音楽を創ることに、共感の「数」を求めても無理なのだと言いきかせるようになった。
そういうものだったのだ、音楽とは。
だから、音楽に対して、嘆いたり腹を立てたりしてもしょうがない。しかし、自分が創る音楽に自分が価値を見いだせないことは不幸だ。……そこが悲劇であると同時に、音楽の奥深さであり、価値なのかもしれない。
 一つ前 |
目次
| 次へ
一つ前 |
目次
| 次へ