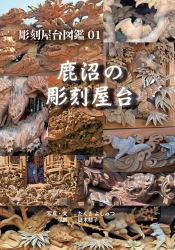ロケ隊一行がようやくやってきた。
ここで初めて本日の講師役である僕と顔を合わせるという趣向のため、ここまで直前の打ち合わせも別々にしていた。なぜ打ち合わせが別々なのかと思っていたが、そういうことだったのね。
「もしかして、あなたが今日のセンセイですか?」「そうです」みたいなやりとりがちょろっとあって、浅草神社へ移動。
目の前の巨大江戸獅子を解説。

「ほら、ここに建立年が刻まれているでしょ。読んでみてください」みたいなやりとりがあって……
ここで出演者3人による狛犬撮影対決、という趣向。
2人が予想外にいいアングルで撮っていたのでちょっとビックリ。しかし、もう1人がごねてごねて……。早くも収拾がつかなくなってきた。
どんな風に編集されているやら……。
前ページで、浅草寺本殿が鉄筋コンクリート製である謎、というのを書いたので、ここではオマケ話として、巨大江戸獅子の奉納者になぜ大工が名を連ねているのかという謎について解説。
浅草神社の巨大江戸獅子は台座が自然石仕立てでかなり特殊。そこに、奉納者と石工の名前が刻まれている。
奉納者の一人が「山川町 大工虎五郎」とでかでかと刻まれているのだが、なぜ大工が、しかも天保の大飢饉の時期にこんな巨大な狛犬を奉納できたのかということについては、狛研理事の
山田敏春さんが興味深い推理をしている。
江戸の歴史は火事の歴史でもあり、その復興が江戸の経済を支えているという一面もありました。
材木商や種々の職人を束ねる大工の棟梁が大きな利益を得たわけです。
吉原に於いても小さい火事は日常茶飯であり、全焼と再建を繰り返しています。
吉原が全焼すると仮宅の営業になります。仮宅の営業は廓内に比べて経費がかからず大層利益があり、建て替えの費用を差し引いても十分残ったと云います。
吉原の主人達は全焼後の仮宅営業で利益を上げ、大工虎五郎は再建工事で利益をあげる。吉原と大工虎五郎はいわば一蓮托生の間柄だったのです。
ちなみに狛犬奉納の前年そして翌年にも吉原は全焼しています。
(狛犬の杜 狛犬ア・ラ・カルト「大工虎五郎の狛犬 山田敏春 2005.10.01)
今も昔も、大きな利権に入り込めた人は巨額の利益を得られるわけなのね。現代で言えば、オリンピック特需にうまく食い込めたゼネコンみたいなものかもしれない。
ちなみに石工は「象潟町 大岩」。
象潟は秋田県の地名だが、秋田の石工が江戸に来たわけではない。本荘藩主が浅草に江戸屋敷を作ったとき、藩の景勝地である象潟九十九島にちなんで屋敷付近を「浅草象潟町」と名づけたのだ。現在の浅草3~5丁目あたりに相当する。





 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ