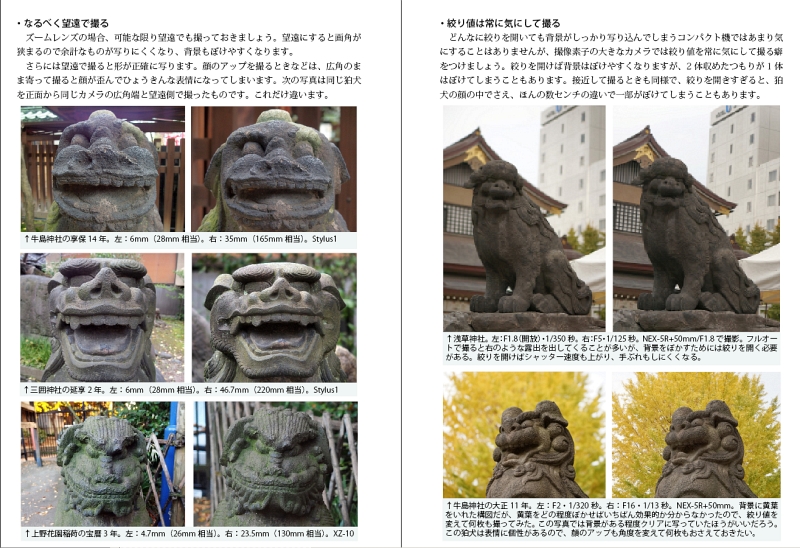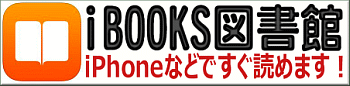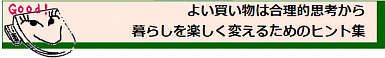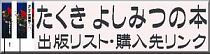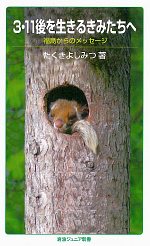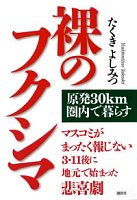2015/12/09
お留守番

ブヴロンのチャバタ(パン)とレトルトのカレーで昼飯
2015/12/11
落ち葉舞う

起きたら窓の外がなんか赤い。雨上がり。落ち葉が濡れてこんな景色に

これがまた腐葉土になるんだね

屋根に落ち葉。窓には雨上がりの空が青く映って……

なかなか全部落ちない

オンデマンド出版に未来はあるか
毎日毎日、残りの人生をいかに生き抜くか、うまく人生を終わらせられるかを考え続けている。
基本的に、僕のような完全なフリーランスは、稼げなくなったときが生活できなくなるとき、という認識でずっとやってきた。
若いときに成功して、歳を取ったら若いときに築いた作品資産で印税生活……っていうのが20代までに思い描いていた人生設計。
それが30代でもしかしたらダメかもしれないと分かってきて(信じたくなかったが)、さらには世の中がどんどんおかしくなってきて、自分の中の「我慢」や「理解」「人間的成長」(?)が現実社会に追いつかない。
税込600円でヒレカツ定食を食べさせてくれる老夫婦は、どうやって生活しているのだろう。
例えば、600円の定食のうち100円が儲けだとする。1日20食作ってひと月25日営業して儲けは5万円。それを1年間ずっと続けても60万円。自営業では年金なんて雀の涙だから……と、いろいろ考えると、老夫婦がやっている定食屋さんには本当に「ごちそうさまでした」と同時に「ありがとうございます」と言いたい。
で、僕も職種は違うけれど、これからはそんな風な生き方をしていこうかと思うのだった。
売れるとかヒットするとか有名になるとか……そういう価値観を完全にリセットし、虚業や一攫千金ではなく、最低限、自分の身を守りながら、小さなことをコツコツとやっていく。
……そんな生き方が惨めだとか失敗だとか思わないようにするためにはどんな方法が残されているのだろうか?
『デジタル・ワビサビのすすめ 「大人の文化」を取り戻せ』でも、そうした自問への自答を書いたつもりだった。今はさらに謙虚、というか、現実的に、慎ましく、ぎりぎりの方法を探っている。
そんなときに、「オンデマンド出版」がかなり使えそうなところまできていることを知った。
オン・デマンドは「需要に応じて」「要求があり次第」という意味で、オンデマンド出版は1冊から製作・注文できる出版システムのこと。オフセット印刷ではなく、コピー機で本を作る。製版がいらないから、少部数印刷に向いている。
最近、このオンデマンド出版が進化して、PDFファイルを預けておくと、購入ボタンを作ってWEB上に置いておけば、1冊から注文を受けて製本までやってくれて、送って、決済も全部オンラインで完了ということができるようになった。
初期費用ゼロで、売れなければお金はかからない。1年に1冊売れた、というようなときでも、問題なくその本は注文者に届けられる。売る側は最初に製品(PDFファイル)を作って預けてしまえばあとはメンテナンスフリー。
1日に1冊弱売れる本があるとする。1年で300冊売れたとする。1冊の儲けを100円に設定すると1年で3万円の儲けにしかならない。でも、そういう本を100種類用意しておくと、300万円の儲けが出る計算になる。
1日に1冊しか売れない本であっても、版元が多種用意すればビジネスとして成立する。
……まあ、そうはなかなかいかないけれどね。そもそも100コンテンツ作るまでに死んでしまうもの。
今までは「売れない本」「売れそうもない本」は、どんなに内容が素晴らしくても、本として残しておくべき価値があっても、本という形にはならなかった。本にならなければ存在していないのと同じで、誰もその「本」のことを知りようがなかった。でも、オンデマンド出版の形を取れば、その本はずっと「存在」が許され、買いたい人は買える。
出版する側にとっても、在庫を抱えてそこに税金をかけられるような二重のリスク、コストから逃れられるので、どんなに売れそうもない「本」であっても売ることができる。
であれば、600円の定食屋さんの心意気で、売れなくてもしぶとくつぶれない本屋さん、というのはどうか。残りの人生を生き抜くひとつの方法にはならないだろうか?
難しいのは価格設定だ。
1冊について100円でも儲けをつけなければただの趣味になってしまう。しかし、オフセット印刷物ならまとまった部数売れればある程度儲けが出るのに対して、オンデマンド印刷物はスケールメリットがまったく図れないから、まとまった部数が出たとしても儲けがあまり出ない。
しかも、オフセット印刷物に比べるとどうしても高くなる。
そのデメリットを考えると、誰もが欲しがるような売れ線の本はまったく向いていない。売れそうもないけれど、ほしい人にはとってもほしい本、つまり、マニアックな本が向いている。
さらには、オンデマンド出版物はカラーのものに向いている。コピー機で作るため、カラーとモノクロのコスト差がそれほどないからだ。
となると、写真集、絵本、アート系の出版物、旅行ガイドブックなどに可能性がありそうだ。A5判64ページフルカラーで送料込み決済手数料込みで千数百円のコスト。あるいはA4判24ページくらいのフルカラー写真集。価格設定をうまくやれば、ほしいと思う人はいるのではないか。
逆に、長編小説などには向いていない。ページ数が増えるから印刷・製本コストがかかる。オフセットと同じ感覚で作ったら、まったくコスト的に合わない。仕方なく、段組にしてギッチギチに字を詰め込んでページ数を減らしたとしても、薄い本に1000円以上出すという購買行動を引き起こしづらい。
だから、小説などは電子ブックに向いている。文字しかないのだから、画面が大きくても小さくても読みやすく流し込みできる。
ところが、Kindleなどの電子出版はなぜか日本ではなかなか伸びない。コンテンツの問題より、やはりタブレットやスマホで文字を読むという習慣が定着しないのだろう。
いずれにせよ、従来のオフセット印刷本、電子本という2つの形態の間を埋めるものとして、オンデマンド出版物が増えていくことは十分に考えられる。
形も、フランス装みたいな製本が増えるかもしれない。
……というわけで、このところずっとその実験に取り組んでいるのだった。
日記の更新が遅れていたのもそういうわけであります。
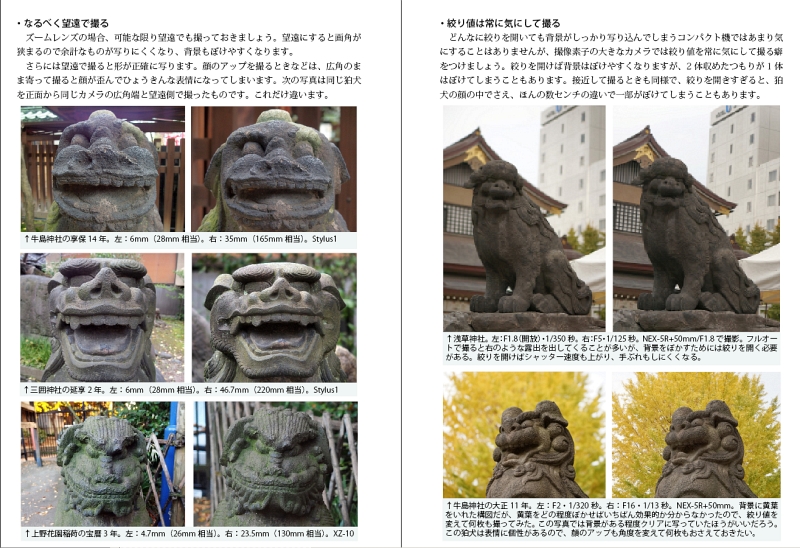
InDesign と格闘中



「第41回国際環境フィルムフェスティバル EKOFILM」ワールドプレミア上映された映画『Threshold:Whispers of Fukushima』が、
日本初の上映会で、福島、京都、栃木を回ります。
2015年12月29日(火曜) Daddy's Cafe(栃木県日光市土沢)にてミニコンサート付き上映会。
18.30開場。監督挨拶、90分の上映の後、映画の音楽監督をつとめたErik Santos氏とたくき よしみつによるミニコンサート。
予約・前売り:1800円、当日・2000円。
予約・問い合わせはDaddy's Cafe(0288-32-2103)へお電話で。
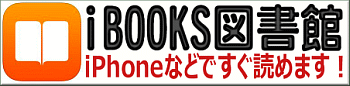

更新が分かるように、最新更新情報をこちらの更新記録ページに極力置くようにしました●⇒最新更新情報
 books
books
 music
music
 目次
目次
 HOME
HOME

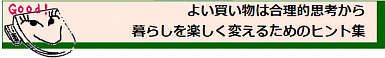
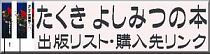

「福島問題」の本質とは何か?
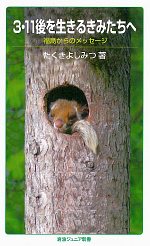

|
『3.11後を生きるきみたちへ 福島からのメッセージ』(岩波ジュニア新書 240ページ)
『裸のフクシマ』以後、さらに混迷を深めていった福島から、若い世代へ向けての渾身の伝言。
複数の中学校・高校が入試問題(国語長文読解)に採用。大人にこそ読んでほしい!
第1章 あの日何が起きたのか
第2章 日本は放射能汚染国家になった
第3章 壊されたコミュニティ
第4章 原子力の正体
第5章 放射能より怖いもの
第6章 エネルギー問題の嘘と真実
第7章 3・11後の日本を生きる
■今すぐご注文できます
 で買う で買う

⇒立ち読み版はこちら
|
|---|
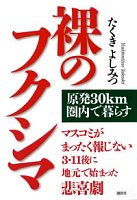
|
『裸のフクシマ 原発30km圏内で暮らす』(講談社 単行本352ページ)
ニュースでは語られないフクシマの真実を、原発25kmの自宅からの目で収集・発信。驚愕の事実、メディアが語ろうとしない現実的提言が満載。
第1章 「いちエフ」では実際に何が起きていたのか?
第2章 国も住民も認めたくない放射能汚染の現実
第3章 「フクシマ丸裸作戦」が始まった
第4章 「奇跡の村」川内村の人間模様
第5章 裸のフクシマ
かなり長いあとがき 『マリアの父親』と鐸木三郎兵衛
■今すぐご注文できます
 で買う で買う
⇒立ち読み版はこちら
|
|---|
 一つ前へ |
| 次の日記へ
一つ前へ |
| 次の日記へ