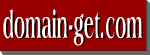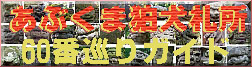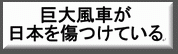この前、ナマズの稚魚か? などと言っていた何かの稚魚。よく見ると、あまりにも劣悪な環境(U字溝に溜まった泥水とヘドロの中)のせいでだろう、尾ひれなどは腐っている。それでも動いているのが哀れ。
手遅れだろうが、復活の沢のほうに移した。
場所を移動しようと一旦、車道に出たところで、排水枡の縁の出っ張りに乗り上げてしまい、あっという間にパンク。
パンク修理キットを持っているので、少し移動してから修理を試みたが、よほど大きな穴が空いたのか、携帯用空気入れで空気を入れるそばから抜けてしまい、穴がどこなのか全然分からない。もしかしてバルブの根元? そうなるとパンク修理キットでは処置できないわけで、チューブごと交換するしかない。
諦めて、ゴロゴロと音をたてて重い自転車を押して家までの坂道を登った。
まあ、いい運動にはなる。
試しに堆積しているヘドロを網で掬い上げてみたら、なんとアカガエルの卵が引っかかった。
こんなひどい場所に産まなければならなかったカエルも哀れだ。
現場は、前後は完全に水がない剥き出しのU字溝。傾斜と枡のおかげで辛うじて水が干上がっていない場所が2m弱残っているという場所。落ち葉やヘドロが溜まり、異臭を発している。
こんなところに産まなければならない理由は主に2つ考えられる。
1)他に水たまりがないから
2)U字溝の垂直の壁を登り切れなくて脱出できなくなったまま、という可能性もある
アカガエルは他のカエルより産卵時期が早い。首都圏では2月末に産むこともある。あの寒い川内村でも、3月には早々と産んでいるやつがいた。
産んだ後、カエルはまた冬眠する。つまり二度寝する。
なぜそこまでして早く産むのか?
オタマジャクシの期間が長いため、早めに産まないと秋までに変態までこぎ着けられないからだ。
ところが、このへんでは田んぼに水が入るのはゴールデンウィーク前後。それまでは水のある場所がない。
川内村でも、田植え前に雨が降って一時的にできた水たまりに大量にヤマアカガエルの卵が産みつけられ、翌日には干上がっているという悲しい光景をいっぱい見てきた。
ここ、日光では、そういう光景はまだ見たことがない。もしかして、日光のアカガエルのほうが学習能力が高くて、じっと田植えの時期まで待っているのかもしれない。
でも、中には待てずに、こんなひどい場所に産んでしまうやつがいるのだな。
このままだと卵は確実に腐るか、田んぼに水を入れるときに一緒に流されてしまうかのどちらかだろう。
迷わず、すくい取って、できたばかりのオオカミ池に避難させることにした。
他にも、この臭い水たまりには、ドジョウが一匹、大きめのツチガエルが一匹、アカガエルが二匹いた。
ドジョウにはびっくりした。よくこんなところで生き延びていたものだ。
ヘドロで酸素も足りないだろうに。
イモリも数匹いた。
田んぼの脇などに、1年中水を溜めている水たまりや、少しでも水が流れているビオトープのようなものを作っておければ、ずいぶん多くの生物が絶滅せずに生き延びられるはず。
でも、そう考える人は極めて少ない。
「生態系が……」と僕が口にした途端に激しい口調で言葉を遮り、「そんなこと言っていても始まらない。人間は自然を壊して生活しているんだ」と、唾棄する人もいた。
その意味では、川内村の人たちのほうが鷹揚だった。カエルやイモリのことを心配して見回っているとは、ずいぶん変わったやつが来たな……という感じで僕を受け入れてくれていた。
自然がまだ残っている場所だったから、農家の人たちの心にも余裕があったのかもしれない。
もう4月も半ばを過ぎたが、田圃の周辺には野草は生えてきていても、カエルなどの姿はまだほとんどない。
夏の間、いっぱい姿を見かけたトウキョウダルマガエルもまだ見ていない。一体どこにいるのだろうか。まだ冬眠しているのだろうか?
身体の小さなツチガエルは、深いU字溝に落ちると這い上がれなくなり、ずっとU字溝の中をさまようことになる。
ツチガエルはオタマのまま越冬するので、冬の間も水が溜まっている場所がどうしても必要。だから、絶滅危惧種になってしまう。昔はあたりまえにいるカエルの代表だったのに。
こんな田舎でも、水たまりひとつないというのは、なんともやるせないことだ。
イモリ以外、みんなオオカミ池へ運んだ。

日付が変わって17日。真夜中にオオカミ池を見に行った。
明るいうちは池の中に潜って姿を見せないカエルたちが、しばらくじっと見ていると、ちらほらと顔を出す。
暗い庭を望遠で撮影。使うのはフジのX-S1。夜景連写モードで撮影。
















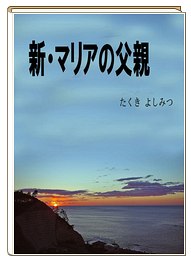















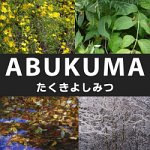
 『ABUKUMA』(全11曲)
『ABUKUMA』(全11曲)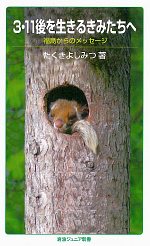
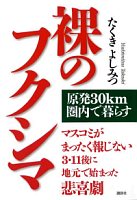
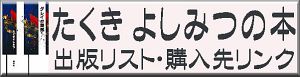

 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ