10/09/13の4
鮫川村の八幡神社

鮫川村の中心部を通って古殿町へ北上。古殿町の和気神社に、大竹寿美さんから教えてもらった「小松布行単独銘の大黒像」があると教えてもらっていたので、確認するのも今日の予定に入っていた。
その前に、鮫川村の八幡神社前を久々に通ったので、野田平郷の狛犬を撮る。
銘は「白河市横町彫刻師野田平業作」。この狛犬を最初に見たのは1999年だから、もう前世紀のことなのだなあ……。
高い位置にあり、片方は必ず逆光になるので写真を撮るのがとても難しい。

籠彫りの珠は破損もなく無事だった

完全な逆光で、きれいに撮るのが非常に難しかった阿像

平郷らしい凝った尻尾の彫り

子獅子もやんちゃ
野田平郷は寅吉の次の世代で、白河を拠点に石工をしていた。平郷の技へのこだわりもまた、寅吉の影響が大きかったことだろう。
さて、古殿町に入り、目的の布行銘の大黒像だが……。

確かに布行の銘がある。「小松布行彫刻」。大正13(1924)年9月というと、布行は46歳。父であり師匠である寅吉の死後9年が経っている。弟弟子の和平は、独立後も長い間、師匠の寅吉を手伝っていた。その和平はこの前年の大正12(1923)年9月、42歳で、西白河郡矢吹町中畑字根宿 八幡神社の灯籠を作っている。
あの銘のない飛翔獅子像がある八幡神社だ。
布行の単独銘の作品は非常に少ない。墓石や墓地の石細工で単独銘のものはあるが、石像はほとんどない。
その意味でこの作品は、父親の死後、ほぼ自力で作ったであろう作品だと思われる。
布行の石工としての腕はいかなるものか……。

背負った袋のふっくら感はなかなかいい感じである

でも前に回ると……
四角い石を削りだして、元の四角形を感じさせないのが石像造りの基本だと思うのだが、この大黒は残念ながら前面がほとんど平面のままで、元の石を想像させてしまう。
40代、脂がのりきった時期であるはずの布行の作品としてはどうなのか。
亀之助布行には申し訳ないのだが、これがもし布行の実力だとすれば、和平との実力差は、今まで想像していた以上のものだったということだろうか。
この大黒像を見たことで、先ほど、鮫川村の熊野神社で想像した、寅吉、亀之助、和平の三者を巡る「銘」への確執ドラマが、ますますリアリティのあるものに思えてきたのだった。
和気神社には別人作の狛犬もあるので、記録しておこう。

鮫川村の飛翔獅子を見た直後なので見劣りするが……

これはこれで十分頑張っていると思う


石工は鮫川村赤坂 鈴木利雄 浅川町里白石 高坂庄司
鮫川村赤坂というのは、ついさっき見てきた熊野神社のある場所だ。浅川町里白石は、寅吉の工房がある福貴作のすぐそば。この二人の石工は、寅吉の弟子筋、あるいはなんらかの縁のある石工だったのかもしれない。
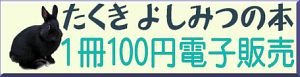
 |
(バナナブックス、1700円税込)…… オールカラー、日英両国語対応、画像収録400点以上という狛犬本の決定版。25年以上かけて撮影した狛犬たちを眺めるだけでも文句なく面白い。学術的にも、狛犬芸術を初めて体系的に解説した貴重な書。
 で注文 で注文
|
 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ
 一つ前へ
一つ前へ 
 次へ
次へ
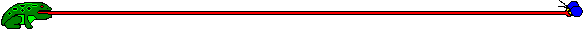
その他、たくき よしみつの本の紹介は こちら
こちら













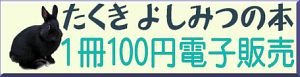

 狛犬ネット入口目次へ
狛犬ネット入口目次へ